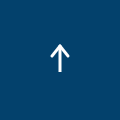IT x 英語でキャリアを築く – 入社1年目の挑戦

本記事では、入社してから1年を迎えたエンジニアより、中途入社してからこれまでの経験を通して、どのような業務を担当してきたか、仕事をするうえでどんな工夫をしているか、業務を通して印象に残っている出来事や学び、そしてスキルアップの取り組みについてお伝えします。
1. 業務内容の紹介
入社後は飲料メーカー様のITインフラ領域を担当するチームに配属となりました。初めはSAP Basisの運用にも携わっていましたが、現在は飲料メーカー様の一部システムを対象とした保守・運用業務がメインです。担当システムの規模感としては本番環境として稼働しているサーバだけで数十台あり、オンプレミスとクラウドの環境が混在しています。サーバOSの種類はWindows系、Unix/Linux系のいずれもあり、データベースやジョブ管理システムも一部扱うため、幅広い知識が求められると感じます。
保守・運用業務の具体的な内容は、各サーバのメンテナンス作業(プログラムの本番機へのリリース、サーバの定期再起動など)、お客様からの問い合わせ事項に関する調査、アラート対応などです。定期作業は運用手順書の通りに漏れなく作業をしていきますが、それ以外のスポット作業では最適な作業方法をその都度調べ、検証しながら決めています。作業後には、今後の参考になるように社内用の手順書を日本語か英語で作成します。
2. 仕事をするうえで工夫していること
何かタスクが割り振られた時は出来るところまで自力で取り組み、自己解決力を身に着けられるように心がけています。例えば、最近はOracleデータベースで検証をした時にデータベースが開けない事態に遭遇しました。この時も、まずは自分でエラー原因を調べて対処法を考えました。調査の結果、エラーの原因はOracleデータベース側が認識しているデータファイルがサーバ上に存在していないためだと分かりました。結局、その後はチームメンバーと相談のうえ、リカバリは実施せず別の検証環境を使うことになりました。ですが、自力で原因を突き止めてリカバリ手順まで準備できたことはOracle初心者の私にとっては大きな一歩になったと思います。
もちろん、自力では解決できない問題が起きた時や不明点がたくさんある場合は上司やチームメンバーに相談します。リモートワークが多くチャットでのコミュニケーションがほとんどなので、あまり長文にならないよう、要点を絞って簡潔に連絡するようにしています。込み入った話をしたい時や実際の作業の様子を確認してほしい時は、オンライン会議ツールを活用して通話をします。チームメンバーとタイミングを合わせて都内のオフィスに出向いて話をすることもあります。普段は自宅で個人のタスクに集中しつつ、必要な時にはオンラインまたはオフラインで相談が出来る環境です。
3. 印象に残っている出来事とそこから学んだこと
これまでで一番印象に残っている出来事は、初めて障害対応をした時のことです。当時先輩社員がたまたま不在だったため、私が率先して障害対応を進める必要がありました。障害の原因調査と復旧方法の検討、対応経緯の取りまとめとお客様への報告など、一連の障害対応を自分が主体となって進めたのはこの時が初めてでした。まだ担当システムへの理解が浅く不安でいっぱいの中、原因を調査したり復旧対応を段階的に試してみたり、必死だったことを覚えています。
そして、対応するうちに、当初の想定とは異なるハードウェア起因のエラーであることが発覚しました。ハードウェア保守ベンダーとのやり取りが必要になったほか、ハードウェア機器交換後のサーバ再起動で想定外の挙動が起きるなど、予想していなかった事態が発生しました。さすがに手に負えずチームに助けを求めると、チームメンバーは他の仕事もある中で時間を割いて障害対応に加わってくれました。最終的にはチームリーダーが解決方法を見つけ、お客様と約束していた時間までになんとか復旧できました。各メンバーはチュニジア、UAE、日本と互いに遠く離れた拠点からリモートワークしていますが、必要な時にはしっかりサポートしてくれます。
これらの作業を通じて、一連の障害対応に主体的に取り組むという貴重な経験が得られました。特に、原因調査や復旧作業の一部分を担当できたこと、自分よりもスキルの高いメンバーがどのように行動しているのかを垣間見られたことは大きな収穫だったと思います。ちなみに、チームの海外メンバーと話す時には英語を使うため、切羽詰まった状況でどうにかして英語を話す、という意味でも良い経験になりました。
4. アヴァクシア入社後に取り組んできた学習やスキルアップ
入社後はSAP Basis、Linux、AWS、AzureなどのITインフラ関連の分野を幅広く学習しています。網羅的に学ぶために資格取得の勉強をすることが多く、2025年中にLPIC(Linuxの資格)とAzureの試験に挑戦する予定です。資格の勉強以外では、実務で必要な知識をその都度調べて学んでいます。例えば、データベースの検証作業を行う時には、Oracleデータベースの仕組みやSQLコマンドを学びました。
インプットには技術書や参考書、UdemyやYouTubeの解説動画を活用します。本や動画を一通り見て概要をつかんでから追加で必要な知識を調べたり、ChatGPTと対話して基礎知識の理解が正しいか確認したり、色々な方法を試してインプットしています。中でもSAP BasisやAzureは英語での解説動画もたくさんあるので、入社してからは語学学習がてらに英語の解説動画を良く見るようになりました。アヴァクシアではUdemyの学習動画や書籍を購入してもらえるうえに、業務に関連する資格の取得費用も補助してもらえるため、学習を続けやすいです。
知識のアウトプットには技術ブログの「Qiita」への投稿、サーバ上での動作検証など、手を動かしてみることを意識しています。頭の中では理解できたつもりでいても、記事を書こうとした時にあやふやな点が出てきたり、実装する時に想定通りにいかなかったりすることがほとんどです。想定外のエラーが発生すると追加で調べ物や検証をすることになり、トラブルシューティングの練習にもなるので良い勉強になっています。誰かに教えられるような得意分野を持てるように、これからも積極的なアウトプットを心がけていきたいと思います。
5. 今後の目標とチャレンジしてみたいこと
これからは、最近アサインしてもらったセキュリティ関連のプロジェクトに注力したいです。海外拠点のメンバーと連携しながらVPNの構築やファイヤーウォールの設定などの作業を担当する予定です。まだプロジェクトが始まっていないので、現在はシステム保守の業務と並行しながらセキュリティ分野の学習を進めています。
今回のプロジェクトでは、ただ作業者として仕事をするだけではなく、設計などの工程を学ぶことも目標にしています。例えば、与えられた情報をもとに設定作業を実施して終わりではなく、なぜこの設定値になるのか理解してから設定を行う、あるいは自分でどのような設定値が適切か考えたうえで設定を行う、というイメージです。機会があれば、一部分でも良いのでネットワーク設計やポリシーの検討などに携わりたいと思います。また、前職でのプロジェクト管理の経験を活かし、海外メンバーとの調整や進捗管理といった運営面にも積極的に関わるつもりです。
この目標の背景にあるのは、早く一人前のインフラエンジニアになりたいという思いです。入社してからいくつかの作業を担当してきましたが、今はまだ上司や他のチームメンバーにタスクを切り出してもらうことや、手順が決まっている定型作業を担当することが多いです。自分で考えて行動できる場面もありつつ、基本的には指示を受けて仕事をする半人前レベルかなと感じています。インフラエンジニアとしてまだまだ知識も経験も浅いので、この機会に成長できるように経験を積み重ねたいと思います。
6. 最後に
私は「IT×英語」のキャリアを求めてアヴァクシアに入社しましたが、思い切ってアヴァクシアに来て良かったなと感じています。チームメンバーの助けを得ながら少しずつITインフラの実務経験を積み始め、海外メンバーとやり取りする中で英語力も格段に伸びました。個人の努力を認めて応援してくれるアヴァクシアで、今後も自分なりのキャリアを模索していきたいです。
私の体験談が皆さんの参考になれば嬉しいです。
アヴァクシアアジアでは、共に成長できる仲間を随時募集しています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。